冠位十二階は、飛鳥時代に聖徳太子が導入した、日本で最初の本格的な官僚制度です。この制度の大きな特徴は、色によって役職の序列を分かりやすく示した点にあります。中でも紫が1番上の位とされており、色の偉い順がはっきり決まっていたことは注目すべきポイントです。
この記事では、冠位十二階の色順番を簡単に解説しながら、なぜ紫が最高位なのか、聖徳太子は何色だったのかといった疑問にも触れていきます。また、この制度がつくられた目的や、家柄にとらわれない登用方針、制度がもたらした効果や時代背景についてもわかりやすくご紹介します。
色の使い方に込められた理由や、儒教などの思想との関わりにも目を向けることで、冠位十二階の深い意義が見えてきます。制度の仕組みを理解することで、当時の社会や政治がどのように動いていたのかをより身近に感じていただける内容になっています。
この記事のポイント
- 冠位十二階における色の順番とそれぞれの意味
- なぜ紫が一番上の位とされたのか
- 聖徳太子がこの制度を作った目的や背景
- 家柄にとらわれない実力主義の考え方
冠位十二階の色順番をわかりやすく解説

冠位十二階は、聖徳太子が導入した日本初の官僚制度の一つです。その象徴ともいえるのが、色で表現された12の位階制度。現代人にとって少しわかりにくい「色による序列」を、この記事ではやさしく、そして論理的にひも解いていきます。
特に「紫が最上位」という点についての背景や理由、また、制度全体の仕組みや歴史的意義についても触れていきます。この記事を通じて、冠位十二階の色の順番だけでなく、当時の政治や価値観にも理解が深まることでしょう。
冠位十二階とは?簡単に解説

ここでは、冠位十二階がどんな制度だったのかを、簡単に説明します。
冠位十二階(かんいじゅうにかい)は、603年に聖徳太子(しょうとくたいし)が作った制度で、日本で初めての本格的な役職のしくみともいえます。この制度では、人を家の名前や生まれた場所ではなく、その人自身の努力や能力で評価することが大切にされていました。昔の日本では、良い家に生まれないと大切な仕事につけないという考え方が強くありましたが、冠位十二階ではその考え方を少しずつ変えていこうとしていたのです。
冠位十二階の大きなポイントの一つは、色でその人の地位をわかりやすくしたことです。それぞれの役職には決まった色があり、その色の冠(かんむり)をかぶることで、まわりの人にも「この人はどのくらいえらいのか」がすぐに伝わるように工夫されていました。
たとえば、紫の冠は一番上の人がつける色で、とても高い地位を表していました。他にも青や赤などの色が使われ、色の順番には意味がありました。このような制度があったおかげで、国の政治がよりスムーズに進み、誰がどんな役割を持っているのかがはっきりしたのです。
序列と色の関係は?
| 位階 | 読み方 | 色 |
|---|---|---|
| 大徳 | だいとく | 紫 |
| 小徳 | しょうとく | 紫 |
| 大仁 | だいじん | 青 |
| 小仁 | しょうじん | 青 |
| 大礼 | たいらい | 赤 |
| 小礼 | しょうらい | 赤 |
| 大信 | だいしん | 黄 |
| 小信 | しょうしん | 黄 |
| 大義 | だいぎ | 白 |
| 小義 | しょうぎ | 白 |
| 大智 | だいち | 黒 |
| 小智 | しょうち | 黒 |
冠位十二階という制度では、役人の地位が「色」と「名前」でわかりやすく分けられていました。この制度は603年に聖徳太子が始めたもので、日本で初めて「人の能力や性格」で評価する仕組みでした。それまでは、どれだけ才能があっても、良い家に生まれなければ大きな仕事に就くことが難しかったのです。そこで聖徳太子は、努力した人や立派な考えを持った人が正しく評価されるようにしたいと考え、この制度を作りました。
この制度では、「紫・青・赤・黄・白・黒」の6つの色が使われていて、それぞれの色には「大(だい)」と「小(しょう)」の2つのランクがありました。つまり、合計で12のランクがあり、それを「冠位十二階(かんいじゅうにかい)」と呼びます。順番で言うと、一番上が「大徳(だいとく)」で、次に「小徳(しょうとく)」、「大仁(だいじん)」、「小仁(しょうじん)」と続き、最後は「小智(しょうち)」が一番下になります。
この名前には、儒教(じゅきょう)という中国の考え方で大切にされている「徳・仁・礼・信・義・智(とく・じん・れい・しん・ぎ・ち)」という6つの徳が元になっています。たとえば「大徳」は、いちばん徳のある人を表しています。「小智」は一番下のランクですが、「知恵」がある人という意味で、ちゃんと価値があるとされています。色と名前の組み合わせで「どんな人がそのランクにふさわしいのか」がわかるようになっていました。
この色の制度は、見た目にもとてもわかりやすかったです。遠くからでも「あの人は高いランクの人だ」とすぐにわかるため、礼儀やルールを守りやすくなりました。たとえば、紫の冠をかぶっている人が現れたら、まわりの人はすぐにその人に敬意を払うことができたのです。このように、色と名前がうまく使われていたおかげで、社会のしくみがきちんと保たれていました。
つまり、冠位十二階の色や順番は、ただのランキングではなく、道徳や人の能力、政治の考えがしっかり反映された制度でした。だからこそ、今でもこの制度は日本の歴史の中でとても大切なものとして語り続けられているのです。
冠位十二階で紫が1番上なのはなぜですか?

紫が最上位に位置づけられた背景には、当時の思想、染色技術の難しさ、そして国際的な文化的影響が深く関係しています。まず第一に、紫という色は古代中国やローマ帝国などでも非常に高貴で尊い色とされており、特別な地位にある人だけが使える色でした。なぜなら、紫色を染めるための染料は自然界に少なく、作るのにも非常に手間とコストがかかったからです。
こうした理由から、紫は「手に入りにくい=価値がある」とされ、権威を象徴する色として扱われていました。日本もそのような国際的な価値観を取り入れ、紫色を最上位の色に据えたのです。また、思想的な側面でも紫は重要な意味を持っていました。儒教の五常(ごじょう)と呼ばれる「徳・仁・礼・信・義・智」のうち、紫は最も重要な「徳」にあたる色とされ、人格的に最も優れた者を示す象徴としてふさわしかったのです。
このように、紫が最上位に選ばれたのは、ただ目立つ色だからという理由ではありません。道徳的な象徴としての意味合い、技術的な希少性、そして国際的に認められていた価値観の融合が、冠位十二階において紫を頂点とする決め手となったのです。こうした背景を知ることで、色の持つ意味が単なる飾りや見た目の問題ではなく、深い思想と文化を反映していたことが理解できます。
聖徳太子は冠位十二階をなぜ作った?

聖徳太子が冠位十二階をつくった大きな理由は、当時の日本の政治がとても混乱していたからです。
その時代、日本では「氏(うじ)」と呼ばれる大きな家の力が強く、政治の中で大きな影響力を持っていました。誰がどんな仕事につくかは、その人の実力よりも、生まれた家柄が重要だったのです。つまり、いくら頭が良くてまじめに努力しても、家柄がよくなければ高い役職に就くことはとても難しかったのです。
このような状況を変えたいと考えたのが聖徳太子です。彼は仏教や儒教といった外国の考え方を学び、「徳(とく)=人としての立派さ」がある人こそ、政治を行うべきだという考えにたどりつきました。この考え方は「徳治主義(とくちしゅぎ)」といわれ、才能や努力のある人が正しく評価される社会を目指すものでした。
そこで聖徳太子は、家柄に関係なく、実力のある人が登用される仕組みを作るために、冠位十二階という制度を考え出しました。この制度では、役職の序列を12のランクに分け、色のついた冠(かんむり)でその地位をはっきりさせました。このようにすることで、誰がどれだけ重要な役割を持っているかがひと目でわかるようになり、国の中のルールや秩序が整いやすくなったのです。
また、聖徳太子は冠位十二階を作るときに、中国の進んだ政治制度をよく参考にしました。当時の中国、特に隋(ずい)や唐(とう)という国では、すでに優れた官僚制度がありました。聖徳太子はその良いところを日本にも取り入れ、日本でもしっかりとした国づくりができるように工夫しました。その結果、冠位十二階の制度は、日本国内の政治の混乱をおさめるだけでなく、外国に対しても「日本はきちんとした国です」と伝える意味を持つようになったのです。
聖徳太子の冠位は何色?
聖徳太子がどの冠位に属していたかについて、はっきりした記録は残っていません。でも、多くの人は、彼が一番上の位である「大徳(だいとく)」だったと考えています。なぜなら、聖徳太子はこの冠位十二階という制度を考え出した本人であり、当時の政治の中心にいたとても大きな存在だったからです。
「大徳」という位は、色で言えば「紫(むらさき)」にあたります。紫という色は昔から特別な意味を持っていて、身分の高い人しか使えない色とされていました。その理由の一つは、紫色を作るための染料がとても貴重で、作るのにも時間とお金がかかるからです。だから、普通の人では手に入れるのが難しく、自然と「えらい人の色」として扱われてきたのです。
また、紫は見た目にも目立って高級感があり、天皇やとても偉い役人などが身に着けていたといわれています。聖徳太子が自分でその紫の冠をかぶっていたことで、「この制度はすごいんだよ」と周りにしっかり伝えることができたのです。そうすることで、みんながこの制度を信じて守るようになり、政治の中でも大きな力を持つことができました。
つまり、聖徳太子が一番高い位にいることで、制度自体の信頼性が高まり、人々の間にも「ちゃんとしたルールなんだ」という安心感が生まれたのです。これは、冠位十二階という仕組みが社会にうまくなじむための大きなきっかけにもなったと考えられます。
冠位十二階の色の順番の意味と目的は?

冠位十二階の「色順番」には、単なる視覚的な区別以上の深い意味が込められています。各色は地位や徳、そして政治的な意図を象徴しており、序列を明確にすることで家柄に依存しない実力主義を目指す制度でした。この記事の後半では、色の選定理由や制度導入の背景、効果などを詳しく解説していきます。聖徳太子がこの制度をなぜ取り入れたのか、当時の時代背景を踏まえて理解することで、「色順番」の本質がよりクリアに見えてくるはずです。
色の理由と冠位十二階における最高位「大徳」の意味
冠位十二階で使われた色には、ただ目で見てわかりやすくするだけでなく、意味のある考え方がこめられていました。特に一番上の位である大徳の色である紫には、たくさんの意味や価値がこめられていたのです。
昔の日本では、色はおしゃれのためだけでなく、その人の地位や人としての立派さを示すサインでした。冠位十二階では、中国から伝わった儒教の6つの徳、つまり徳、仁、礼、信、義、智という考えに合わせて、色と役職の名前が決められていました。紫はその中でも「徳」をあらわす色で、一番立派な人にふさわしいとされていたのです。
また、紫という色そのものにも特別な理由がありました。昔の染物では、紫の色を作るのがとてもむずかしく、材料も少なくて高価でした。そのため、紫の服や冠はお金がある人や偉い人しか持てなかったのです。そうしたことから、紫は自然と「えらい人の色」として知られるようになっていきました。
紫の冠をかぶる「大徳」という位の人は、ただ名前が立派なだけではありません。実際に、国の大切な仕事をまかされる立場で、たとえば天皇の近くで相談にのったり、大事な会議に出たりといった役目がありました。この位につくには、知識や経験だけでなく、まじめで思いやりのある人であることも大切だったのです。
このように、色とその人の立場や徳がつながっていたことで、誰が偉い人なのかが見た目ですぐにわかり、社会のルールが守られやすくなりました。紫の冠を見れば「この人はすごい人だ」とすぐにわかるので、まわりの人も自然と敬意をもつようになったのです。
さらに、大徳の人はまわりのお手本になるような行動をすることが求められていました。たとえば礼儀正しくしたり、人にやさしく接したりすることで、社会全体によい影響をあたえることができたのです。
冠位十二階の中で大徳という位は、ただ一番上の役職というだけでなく、徳のある人が政治をするという理想の考え方の中心にある存在でした。このように、色と意味と役割がしっかりつながっていたことで、この制度には強い説得力がありました。
冠位十二階の目的は?

冠位十二階の制度は、「どんな家に生まれたか」ではなく、「どれだけ努力し、どんな力を持っているか」で人を評価しようという考え方から生まれました。
昔の日本では、政治の中心に立つのはほとんどが名家や力のある家に生まれた人たちでした。特に「豪族」と呼ばれる大きな家の出身者が政治を動かすことが当たり前で、実力があっても身分が低いと高い役職に就くのは難しかったのです。そんな社会を変えようと考えたのが、聖徳太子です。彼は人の中身や実力、まじめさや思いやりの心を重視して、それにふさわしい地位を与える社会を目指しました。そして、その考えを形にしたのが冠位十二階という制度でした。
冠位十二階は、地位を12のランクに分ける仕組みで、それぞれの役職には「冠位」という名前がつけられました。これにより、役人一人ひとりの立場や仕事がわかりやすくなり、誰が何をするべきかが明確になったのです。こうして政治の混乱が少なくなり、国のしくみが整っていったのです。役職の順番は色でも分けられていて、紫が最も高く、黒が一番下でした。これにより、見た目でも地位がすぐに分かるようになり、社会全体のルールや礼儀も守りやすくなりました。
さらに、聖徳太子はこの制度を作るとき、中国の先進的な政治のしくみを学び、それを日本風に工夫して取り入れました。特に隋という国の制度を参考にしました。中国の政治制度はよく整っていて、能力のある人が役職につける仕組みができていたからです。聖徳太子は、その良いところを日本に合うように直しながら取り入れました。こうした新しい考えがあったからこそ、冠位十二階は画期的な制度となり、日本の政治が大きく変わるきっかけになったのです。この制度は、役職を決めるだけでなく、人の生き方や社会の考え方にも大きな影響を与えたのです。
冠位十二階と家柄の関係について
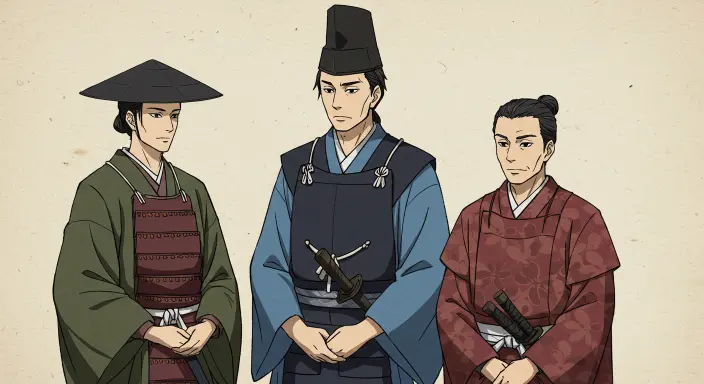
冠位十二階の制度がとても新しかった理由の一つは、家柄にとらわれず、人の能力や人柄を大切にした点です。
昔の日本では、大きな力を持つ家、いわゆる「豪族(ごうぞく)」の家に生まれた人が、政治の中心に立つのが当たり前でした。そのため、どれだけ才能があっても、普通の家に生まれた人が高い役職につくのはとても難しかったのです。しかし、冠位十二階が始まると、どんな家に生まれたかよりも、その人がどんな努力をし、どんな考え方を持っているかが大切にされるようになっていきました。
この制度の考え方は、「徳のある人、つまり人のために正しいことをしようとする立派な人が、えらい立場になるのがふさわしい」というものでした。そうした考え方を制度にしっかり取り入れたことで、努力した人が報われやすくなり、「がんばれば自分も上に行ける」という希望が生まれました。
もちろん、すぐに家柄の力をすべてなくすことはできませんでした。当時の社会では、まだまだ家の名前や立場が強い影響を持っていたからです。しかし、それでも「実力や性格で評価される世の中に変えていこう」という大きな一歩を踏み出したことには、大きな意味がありました。
このような新しい考え方は、後に作られた「律令制度(りつりょうせいど)」にもつながっていき、日本の政治の形を大きく変えるきっかけになったのです。つまり、冠位十二階という制度は、ただ色や名前で人の立場を表すだけの仕組みではなく、日本の社会をもっとよくするための新しいチャレンジでもあったのです。
冠位十二階の効果は?
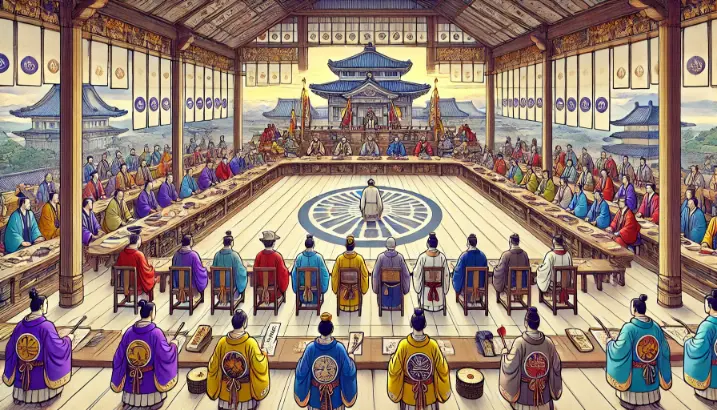
冠位十二階の導入によって、当時の日本の政治の仕組みは大きく動き出しました。まず注目すべき点は、政治の基盤となる「官僚制度」がきちんと作られ始めたことです。今までは誰がどんな仕事をするのかがあいまいなままでしたが、この制度ができたことで、役割がしっかりと分かれ、仕事がスムーズに進むようになりました。これは、国のしくみを整えるためのとても重要な一歩でした。
そしてもう一つの大きな変化は、「中央集権(ちゅうおうしゅうけん)」の仕組みが動き出したことです。これは、地方のバラバラな力をまとめて、中央の政府が日本全体をしっかりと管理しようとする考え方です。今まで各地の有力な豪族が自由にふるまっていた状況から、日本という国が一つになって進もうとする大きな流れが始まったのです。
この制度の背景には「徳治主義(とくちしゅぎ)」という道徳的な考え方もありました。これは、強い力を持っている人ではなく、正しい行いができる人こそが政治を動かすべきだという考えです。聖徳太子は、心の立派な人をえらい立場にすることで、良い政治ができると信じていました。この考え方は、今の時代にも通じるとても大事なものです。
とはいえ、この制度にはいくつかの問題点もありました。制度としては素晴らしいものでしたが、現実にはまだまだ「豪族(ごうぞく)」と呼ばれる大きな家の力が強く、その影響をすぐに消すことはできませんでした。豪族たちは自分たちの立場を守ろうとしていたため、新しい制度がすぐに広まるわけではなかったのです。
それでも、冠位十二階が導入されたことは、日本の政治の仕組みを少しずつ良くしていこうとする本気の取り組みだったことは間違いありません。この制度がきっかけとなって、その後の律令制度など、もっと大きな改革へとつながっていったのです。まさに日本の歴史にとって、大きな一歩だったといえるでしょう。
冠位十二階の時代はいつ?
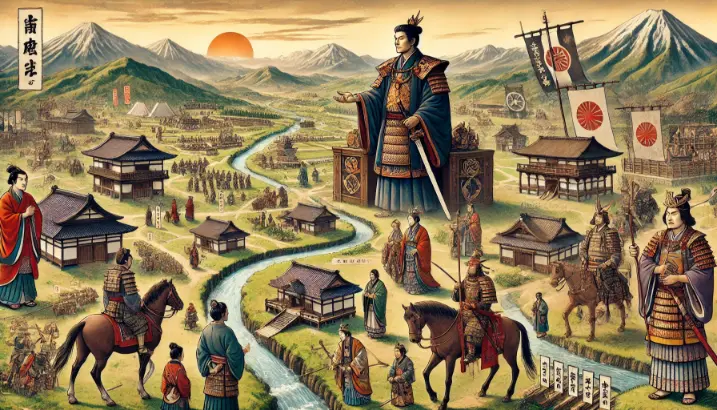
冠位十二階が始まったのは、603年の飛鳥時代のことです。このころの日本は、今のように政府や法律がしっかり決まっているわけではなく、地方にはそれぞれ強い力を持った豪族(ごうぞく)という家の人たちがいて、自分たちの土地を治めていました。つまり、国全体として一つにまとまっていたわけではなく、あちこちに力のある家が分かれているような状態だったのです。
そんな中、聖徳太子という人物が現れました。彼は中国の進んだ政治制度や考え方を学び、「日本も一つのまとまった国にしたい」と考えるようになりました。そのために目指したのが、中央集権(ちゅうおうしゅうけん)という、一つの政府が全体をまとめる国の形です。そして、その考えをもとに、聖徳太子が推古天皇(すいこてんのう)のもとで政治を任されていたときに考え出したのが「冠位十二階(かんいじゅうにかい)」という制度でした。
この制度は、それまでのように「どんな家に生まれたか」ではなく、「どれだけ努力して力があるか」「人としてどれだけ立派か」といったことをもとに、人の地位や役職を決めようとする新しい仕組みです。今でいう「能力主義」に近い考え方で、これまでのように家柄だけで偉くなれるわけではなくなりました。こうした考え方は当時としてはとても進んだもので、多くの人にとって新鮮な驚きがあったでしょう。
この冠位十二階の制度は、後にできる「律令制度(りつりょうせいど)」という、日本の政治や法律の基本となる仕組みのもとにもなりました。つまり、この制度がきっかけで、日本の国の形は少しずつ整っていき、より安定した政治が行えるようになったのです。冠位十二階は、ただのルールではなく、日本が一つの国として成長していくための大きな一歩だったといえるのです。
冠位十二階の色の順番に込められた意味と背景のまとめ
この記事のまとめ
- 冠位十二階は603年に聖徳太子が制定した制度である
- 色の順番は紫・青・赤・黄・白・黒の6色で構成されている
- 各色に「大」と「小」の2階級があり、合計12の位がある
- 紫は最上位の色であり、権威と徳を象徴している
- 色には儒教の徳目「徳・仁・礼・信・義・智」が対応している
- 紫が高位なのは染色が難しく高価だったため
- 聖徳太子は家柄に関係なく人材を登用しようとした
- 冠の色によって役職の高さが視覚的に分かる工夫がされていた
- 「大徳」は最も高い位で紫の冠をかぶる
- 聖徳太子自身も「大徳」だったと考えられている
- この制度は中国の官僚制度を参考にして作られた
- 家柄ではなく努力と能力を評価する実力主義が導入された
- 社会に秩序をもたらすための視覚的な序列制度でもあった
- 制度は中央集権化を進める一歩となった
- 後の律令制度につながる基礎的な枠組みを形成した
冠位十二階では、地位の高い順に紫、青、赤、黄、白、黒の6色が使われ、それぞれに「大」と「小」のランクがありました。これにより全部で12階級が作られました。
紫が最も高い位で、黒が最も低い位です。色ごとに意味があり、徳や礼儀、信頼などの価値観を表しています。見た目で地位が分かるため、秩序が保ちやすい仕組みになっていました。
この制度を通じて、実力や人柄が評価される社会を目指していたことがわかります。色の意味を知ることで、制度への理解を深めていきましょう。
こちらもおススメ



